(その三)
敗退に敗退を重ねる国外での負け戦さと並行して、国内では「勝った」「勝った」の大本営発表にかかわらず、‘43年後半からは、学徒出陣や出征・徴用・学徒動員と、国策によって離散させられる家族がふえてきた。
‘44年に入る頃には、都市疎開政策が開始されて建物強制疎開・工場疎開で転廃業を強制された上に家屋を奪われ、住み慣れた地を追われる人も出て来た。また老幼婦女の縁故疎開が勧奨され、さらに、‘44年8月からは学童集団疎開によって、子ども達が親から引き離されていった。
食糧をはじめとする物資の欠乏、統制、隣組などによる日常生活の監視など、日々、暮らしにくくなっていった。
その上、‘44年10月の那覇空襲以後、都市への無差別爆撃である空襲、今風に言えば「空爆」が始り、直接に生命の危険にさらされるにつけ、「一億一心」を誓った筈の人々も、右往左往しはじめ、厭戦的な気分が蔓延してきた。
このままでは暴動・共産革命が起こるかもしれないと怖れた近衛文麿は、‘45年2月「国体護持」を願って天皇に戦争中止、つまり敗戦を進言した。にもかかわらず、原爆投下の8月まで延々と引きのばされたのは、天皇制をいかに護持するか。要するにポツダム宣言を受け入れても、国体護持の承認を得られるかどうかを確かめるための時間かせぎだった。
その半年間に沖縄をはじめ国外・国内の犠牲者は、非常に多く集中している。
そうした事実を通して、国とは国家とは一般人の生命よりも、国の存続こそ優先されることを、私たちは身をもって知ったのである。
明治維新以来築き上げてきた国体、つまり天皇制をいかに扱うか、このことは為政者にとって欠かせない大問題であった(☆1)。
だからこそ憲法論議が憲法特別委員会に移されても、
「・・・各党委員の質問の矢は『主権の所在』、『天皇の権限』に向って注がれ、これが相次ぐ質問の糾弾に憲法専門大臣の金森さんは答弁に□□『主権は天皇を含む国民に在る』とか『天皇は国民の憧れ』などと焦点をぼやかそうと・・・」(46.7.8)
といった場面がくり返されている。
少し長くなるが一つの例を引くと、前日(46.7.7)の「議会展望」という欄の記事では、「天皇の本質論と第七十三条の解釈論」という見出しで、野坂参三と金森徳次郎のやりとりが記されている。これをわかり易く質問と答弁形式にしてみると、
野坂―『天皇とは何か』心の中にあるあこがれか、イメージかそれとも機関か、自然人か
金森―血統の繋がりの中にある人である
野坂―それでは自然人か
金森―血統の繋がりの中にある自然人である
野坂―では天皇の公正無私とは血統に繋がる性質か
金森―公正無私たるべきと云った筈である
野坂―然らば天皇の公正無私は誰が保証するのか
金森―内閣の助言と承認の上にいる天皇たる事により保証される
(46.7.7)といった天皇論がなされている。
>>
また、6月中の首相宛投書数566通、これは前月に比して139通増加しているそうだが、投書の第1位は、なんといっても食べることにあえいでいた人々の“食糧よこせ”の痛切な叫び。
第2位の政治問題に関しては、 「・・・天皇及び皇室の問題と内閣批判に関するものが極めて多く、憲法については、政府草案並びに改正そのものに反対して君主制を主張するものや・・・」(46.7.8)と天皇制存続を願う声も多々あり、それが「投書」という行為をする人々の反応であったことがわかる。
ついでに言うと、敗戦以前には、民衆が政府や為政者にもの申すなどということは考えもつかなかっただろう。
ところが 「首相宮へ信書お許し 直接民意御聴取 言論暢達に畏き思召」(「朝日新聞」45.8.31東京都立日比谷図書館蔵縮刷版)と、東久邇首相自らが「国民からの手紙を諸君、私は皆さんから直接手紙を戴きたい」と呼びかけた。
以後、政府・天皇・司令部への投書が奨励された。
敗戦後1年も経ったこの頃、たくさんの人々がマッカーサーに手紙を出したり、首相宛に意見を述べたりする投書がどんどん増えていった。
(☆2)
「茨城新聞」でも、「アンテナ」とか「県民の声」という欄が設けられて投書を受け入れている。
ところで話を前に戻すと、当時の「日記」を寄せてくれた私の友人も、その中に「新憲法で天皇は国民のあこがれの的と云われるようになった。共産党は『天皇などいられなくてもよい』と云う主義でありますが天皇は日本の国におられないと国がまとまりません」
と子どもながらに正直に書きしるしていることは前篇ですでに紹介した通りだが、これは当時の社会的雰囲気を受けての感想なのだろう。いや現在でもそう思って口にする人に出逢うことがある。
また、7月21日の記事には「新憲法条規違反の天皇制擁護は取締る」と金森国務相が答弁したとあり、天皇の地位をめぐって、これを擁護するような運動が起きた場合を想定した議論があったことを見れば、当時の人々が敗戦後も天皇制に相当に縛られていたことがわかるのである。
>>
衆院を通過した草案が貴族院に送られた秋、ここでも前文と第一章「天皇」の審議で手間どり、9月14・15両日の政府と貴族院とのやりとりは、「第三章の『国民』は天皇を含むか否か」で解釈が対立した。両者の見解をまとめると、
- 政府
- 一、天皇の地位には公私の二つがあり、権利義務については、公の場合、象徴たる地位にかんがみ、一般国民とは差別されねばならぬ
- 一、天皇を国民から切離し、超越した存在とするとどうしても治める者と治められる者との対立感が生じる。それよりも天皇を国民の中に抱擁してゆく考え方の方が国民感情に合っている
- 一、現行憲法の『臣民』は対立的な意味を持つ。『国民』は『臣民』の意ではない
- 委員
- 一、第三章の国民の権利義務の規定は、現行憲法の臣民の権利義務の規定を受継いだものであり、従ってその国民は臣民の意ではないか(佐々木惣一)
- 一、天皇は公私を超越した存在である(松本烝治)
- 一、天皇が国民の上の存在であることは国民感情では当然のことである(小山完吾)(46.9.18)等々である。
旧憲法下、貴族院は、皇族・華族・多額納税者など、勅任議員から成り立っていた。彼らが「皇室の藩屏(はんぺい。皇室を守護する垣根)」を自認していた階層であったことを考慮すれば、貴族院憲法委員会の委員たちが、天皇は戦後も超越した存在であると見るのも当然のことであった。
しかもそのような感情は、貴族院に属するような人々ばかりでなく、先にも述べたように、大人から子どもまで、天皇のいない社会は考えもつかなかった事例はいくらでもある。
敗戦後すぐに全国から宮城(きゅうじょう。皇居)奉仕に参加する人々は引きもきらず、敗戦1年後のこの時点で100団体、5千人の人が奉仕活動に出向いていると報道されている(46.8.28)。
此の地茨城からも、青年団有志が奉仕団となって、皇居の焼跡の整理や清掃、畑づくりに食糧持参で泊り込み、感激しながら奉仕する姿が、記事(47.4.17)に出てくる。
(☆20-1-8)
明治以来80年、学校教育と国家神道で注入され内面化された天皇崇拝の感情と不敬罪の怖れで、天皇をあがめ奉る感情は一朝一夕に消え去るものでないことを実感するのである。
しかもそれまで現人神として、白馬にまたがる大元帥(だいげんすい)の姿で、遠い存在であった天皇が、皇居内の勤労奉仕団にねぎらいの言葉をかける、ごく身近な存在として報じられるようになった。
それは、日本全国で展開された戦後巡幸での熱狂的な歓迎ぶりにも、共通して見ることができる。1946年11月に当地茨城に「生産・復興状況ご視察」の名目で来県した天皇の姿は、「人間天皇をお迎えする」「二○○万県民 感激に沸く」という見出しで詳しく報じられ、声をかけられた人々の感涙にむせぶ写真が載せられている。(46. 11.18−21)
そのような雰囲気の中での憲法改正であったが、戦後初の東大総長となった南原繁は、新憲法公布の11月3日、これを祝して安田講堂で記念祝典を催し、学生たちに向って新憲法の精神革命を説いている。
「・・・今や天皇は政治に関する権能を有せられず、単なる儀礼的、形式的存在となり、もはや国家意志の醸成そのものに関与せられなくなったことである。この故に旧憲法第一条の所謂君主主権宣揚は根本的変革を遂げる。『主権在民』という立場から『国体』観念は、その解釈においても重大変革を生じ、わが国統治権の根拠は古来の伝統にかかる神権的□□□権威から民族的な国民の意志に置き換えられたのである。これこそ正に肇国以来の精神革命期でなくて何であろう。・・・」(46.11.5)
「天皇制と人民主権の接木」は、右のような過程を踏んで出発したのだった。つまり天皇の救済と憲法制定は、言ってみれば日米の合作によって、天皇制と民主主義という相反する二つのものが同時に備わって誕生した。
(☆3)
☆1佐藤達夫『日本国憲法誕生記』中公文庫、1999、p.103
☆「“あこがれ”誕生 枢密院の審議が終ると、わたしたちは議会での説明の準備に全力を集中した。
いちばん力を入れたのは、国体と主権の問題であった。・・・
そこで、金森さんを中心として、連日、研究を重ねた。この改正によって日本の国体が変るかどうか、
ということについては、まず、国体は主権の所在によってきまるというような一切の既成の概念を捨て、白紙にもどって考えなおした。これについては、たしか、穂積八束博士だったように思うが、とにかくむかしの憲法学者の本に、国体とはそれが変れば国がほろぶ、つまり国の同一性がなくなる――そういった“国の基本特色”だという趣旨のことがあったのにヒントを得て、そこから出発した。
その考えのすじ道をたどるとこうである。――
建国以来今日まで、日本の国の同一性に何等の変更もなかったということは国民の確信だといえよう。そしてそれは常に天皇の存在と結び付いている。しかし、天皇の政治上の地位について歴史をふりかえって見ると、それには時代によって大きな消長があり、全然政治の実権から離れられていた時期もある。そういうように見てくると、こんどの憲法改正によって、天皇が政治の権力から離れることになっても、この意味での国体(国の根本特色)が変ったとはいえないのではないか、ということである。
こういう角度から、日本の国体というものを見た場合、結局、天皇の存在を離れてそれを考えることができない、ということになるだろう。もっとも、天皇の存在といっても、それが単なる“天皇家の存在”ということだけに止まるものでないことも明らかだ。それならば、いったいそれはどういう立場、どういう性格での天皇の存在であったか、というように洗って行って、とどのつまり、それは、天皇というものを、心理上の媒体として、国民が結びついて日本という国が構成されている、ということにちがいない。そして、この根本特色は、こんどの改正でいささかも変るものではない。
――という結論に達したのであった。
そこで、そのことを説明するについて、どういうように表現するか、何かいいキャッチ・フレーズはないかと、いろいろ知恵をしぼったあげく、はじめ“天皇を媒体として”とやっていたのを、“天皇を敬愛の的として”というように変えて見た。
しかし、これでは、ちょっと色が出すぎはしないか、というようなことで比較的無難なことばとして、“あこがれの中心”に落ちついたのであった。それにしても、このことばはいかにも少女趣味で、きざに聞こえる心配もあるから、答弁資料は“いわばあこがれの中心として”ぐらいにしておこう、ということにした。いまそのときの資料の一つを引き出して見ると、それは次のようになっている。
問 憲法改正によって、国体の変更を来さないか。
答 「国体」とは、国家の個性を云うものと考える。而して、わが国の国体は「国民の心の奥深く根を張っている天皇とのつながりによって(いわば天皇をあこがれの中心として)国民全体が結合し、もって国家存立の基底を成している」ということに在ると信ずる。本改正は、この国家存立の基底を変更するものではないから、これによって、国体の変更を来すことはない。
(従来、天皇が統治権を総らんせらるることをもってわが国体なり、とする考え方があるが、かかる考え方をもってすれば、憲法改正によって、国体は変ったことになる。しかし、この考え方は、政体の面に着眼しての考えであって、深く国体の真髄に徹したものではない。すなわち、天皇が統治権を総らんせらるることは、政体の問題と考える。今回の憲法改正によりかかる政体的の面においては大きな変更を生ずるが、これは国体の変更ではない。)
この“あこがれ答弁”は、議会がはじまると、たびたび金森さんの口にのぼった。その結果、キャッチ・フレーズとしても、少しくすりがききすぎて、新聞のゴシップなどでは、金森さんはさっそく“あこがれ大臣”の異名を奉られ、憲法草案は“あこがれ憲法”ということになり、さては、この“あこがれ”が日常会話のはやりことばにさえなってしまった。これには“言い出しべえ”のわたしも、いささか首をすくめたのであった。」
(ブラウザの「戻る」をクリックすれば、本文の☆に戻ります)
☆2‐1 マッカーサー宛に日本人が大量の手紙を送ったことは、次の二書で見られる。
袖井林二郎『拝啓マッカーサー元帥様―占領下の日本人の手紙』大月書店、1985年。
川島高峰『占領軍への50万通の手紙』読売新聞社、1988年。
川島高峰p.22には―
「GHQ当局への投書は占領政策の進展と共に増える傾向にあったが、1945年末までの投書総数は8百通前後であった。他方、東久邇宮内閣は組閣時から、国民に投書を求める旨を発表していた。これは幣原内閣にも引き継がれ、1945年11月7日付の『毎日新聞』によると組閣以来、約一か月で千通の書簡が寄せられていた。したがって、敗戦直後のGHQへの投書は日本政府宛のものに比べるとはるかに少ない。
GHQへの投書が一か月千通の量に達するようになるのは、1946年4月以降のことである。・・・占領期の全期間で投書は約50万通へと膨れ上がっていた。」
☆ 2 - 2 日高一郎『日本の放送のあゆみ』有限会社人間の科学社、1991、p.108―「『建設の声』は9月19日から始まった。敗戦日本の再建に役立たせようと、言論表現の自由が与えられた国民の声を積極的にマイクに取り入れようというもので、社会のあらゆる問題についての聴取者の投書をそのまま放送した。自分の意見を電波に乗せたいという人々から一日に300通もの投書が寄せられた。」
☆ 2 - 3『朝日新聞社史 昭和戦後編』12-14頁によれば、―
「『天声人語』と『声』 終戦直後の紙面は二ページで、構成を大きく変える余地はなかったが、20年9月6日から朝刊のコラム『神風賦』を『天声人語』と改めた。『神風賦』の語感が時代にそぐわなくなったのである。・・・
また東京の投書欄『鉄箒』も昭和20年11月1日付の紙面から
『声』に改められ、スペースもぐっと拡大された。民主主義の時代にふさわしく、より多くの国民の声をきく欄にしたいからであった。『声』欄の発足直後には著名人の長文の投書が連日のようにのった。」
☆ 2 - 4 ‘45年12月12日の朝日新聞には、「11月中の投稿総数は2889通、一日平均963通に達し、「鉄箒」当時に比し圧倒的な投稿数となってゐる。」とある。その内訳は、天皇制問題174通、食糧問題344通、政治問題(憲法改正、政治機構、戦争の責任)347通、教育問題175通、ほか、である。が、投書者のうち女子数は、天皇制問題のうちに22名、政治問題のうちの婦人参政権に関して12名とあるだけで、全体に占める数は不明である。
☆ 2 - 5 ‘51年10月新設の朝日新聞の「ひととき」が、翌春から女性専用投書欄となり、反響がひろがり、全国各地の新聞にも同様の女性投書欄が設けられる。
影山三郎『新聞投書論 民衆言論の100年 』(現代ジャーナリズム出版会、1968年)は、「昭和29年における投書激増のなかには、大量な女性の投書がふくまれていたのである。」ことを、「女性投書の爆発的はんらん」(p.274)とよんでいる。
この時期の、‘54年9月16日調査「あなたは新聞へ投書したことがありますか」への回答は、「ある」は.3%、「新聞を読まない」が16.9%である(新聞世論調査連盟『調査一覧2』1955年、79頁)。
それから14年後の1968年2月朝日新聞「声」欄へのこの月の投書総数8704通(男6382、女2290、団体19、不明13)である(影山三郎『新聞投書論』p.273)。
影山三郎の、「有権者の過半数を占める女性が「大衆」というものの有力な構成分子となり、女性の参加によって倍加された社会的な大衆が政治的な発言をしはじめたことは、明治以来の近代国家としての日本の政治に、かつて考えることもできなかった経験である。」(p.275)という指摘にもかかわらず、投書は依然としてごく少数者のすることであり、しかも圧倒的に“男のすること”であった。
“男女共同参画”が国策となったはずの2002年11月も、朝日新聞(東京・大阪・西部・名古屋各本社)への投稿数は6325通。うち男性3834、女性2491である。(朝日新聞『声』2002.11.30)
参考:奥田暁子編著『女たちは書いてきた―「ひととき」に見る現代女性史』径書房、1986。
平野恭子・池田恵美子「新聞の女性史」『女と男の時空〔日本女性史再考〕?』藤原書店、2001。
☆ 2 - 6 新聞投書について、山本武利『近代日本の新聞読者層』(法政大学出版局、1981、p.364)は、次のように述べている―
「新聞投書からみた明治期の新聞新聞投書の性格や内容は新聞と読者の相関によって規定される。つまり新聞社の読者観、編集、営業方針と、読者の新聞観、社会意識とのダイナミックな相関のなかで、そのときどきの投書欄が形成され、変化している。・・・
明治期の投書の歴史をふりかえってみると、初期と後期のそれが本質的にちがっていることがわかる。新聞が明治初期の記者と読者とが一体となって作成する同人紙的なもの、あるいは記者と読者の立場が代る互換性をもつものから、読者を排除して記者が作成するもの、あるいは読者を消費者とみる企業的なものへと転換している。・・
新聞投書からみても、明治後期に読者の受け手化、記者の送り手化という読者と記者の乖離が決定的になったことがわかる。投書は企業サイド、企業ベースでしか経営者側から考えられなくなる。一般読者が投書に強い関心をいだいているときとか、社会平穏のため社会的情報が欠乏しているときとか、新聞キャンペーンの論理を世論=投書の「支援」で擬装化させるときしか、投書欄は設けられなくなった。投書欄はそのときどきの新聞の編集方針、営業方針の観点から、伸縮自在に調節できる安全弁となった。
一方、読者自身も受け手として意識し、主体的に新聞へフィードバックしたり、参加したいという意欲をほとんど失ってしまう。新聞が権力に弱く、権力との闘いにつねに敗北していることも、読者の参加意欲をすりへらした。日本人が歴史的にもっている権力への無条件な服従心や官尊民卑の心情も、新聞の企業化、「不偏不党」化、体制化とともに、投書活動を停滞させる根因となった。ことに新聞が投書者をかばいきれず、権力に売り渡した事例も、権力批判的な投書の減少をもたらし、さらには一般読者の投書への関心を低下させる一因となった。このように明治後期に大正期以降の日本型新聞の基盤が固まったことが、新聞投書の変遷過程という視覚からも見なおせたと思う。」
(ブラウザの「戻る」をクリックすれば、本文の☆に戻ります)
☆3竹山昭子は『ラジオの時代―ラジオは茶の間の主役だった』(世界思想社、2002、p.297以下)に、『朝日』『読売』『毎日』の1945年8月15日以降‘46年12月までの投書と、見出しにおける「天皇制」の出現数を検討した結果―
「事実、本章が数字をあげて実証してきたとおり、放送、新聞、雑誌における「天皇制論議」は、いずれも四六年一月をピークとして三、四月から退潮を始めている。新憲法案が衆議院本会議で可決、成立したのは46年10月7日、公布は11月3日だが、国民もマスメデイアもそれ以前に象徴天皇を受け入れ、論議することを止めてしまったのである。
・・・戦後のマスメデイアにおける「天皇制論議」がアメリカの占領政策によって解禁され、GHQの指導のもとで活発に論議され、やがてアメリカの占領政策のなかで急速に退潮していくことをみてきた。まさに、マスメデイアにおける「天皇制論議」の解禁から退潮への過程は、アメリカの日本占領政策そのものであったのである。」
「茨城新聞」も、国会審議報道は天皇制に集中しているが、投書や一般記事の傾向は、竹山の指摘と軌を一にしている。
(ブラウザの「戻る」をクリックすれば、本文の☆に戻ります)
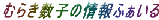
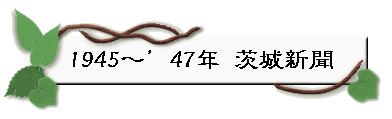
 Links to other sites on the Web
Links to other sites on the Web
 第一章「茨城新聞」に見る「憲法」制定過程(そのニ)に戻る
第一章「茨城新聞」に見る「憲法」制定過程(そのニ)に戻る 第二章「憲法」普及の取り組みと公布・施行の賑々しさ(その一)に進む
第二章「憲法」普及の取り組みと公布・施行の賑々しさ(その一)に進む 目次
目次 ホーム
ホーム Links to other sites on the Web
Links to other sites on the Web 第一章「茨城新聞」に見る「憲法」制定過程 (そのニ)に戻る
第一章「茨城新聞」に見る「憲法」制定過程 (そのニ)に戻る 第二章「憲法」普及の取り組みと公布・施行の賑々しさ(その一)に進む
第二章「憲法」普及の取り組みと公布・施行の賑々しさ(その一)に進む 目次
目次 ホーム
ホーム